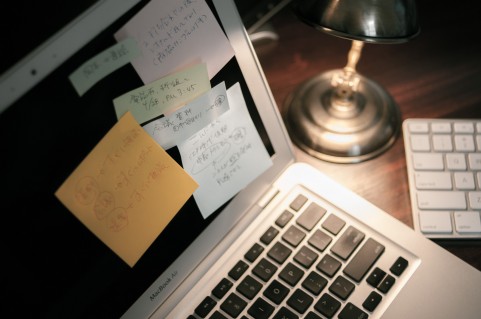 統計上の景気回復期間は既に、57か月続いたいざなぎ景気を超えたとされています。また、有効求人倍率の改善によって足元では人材の採用が難しくなってきており「人を募集しても全然応募がないよ」といった声も聞こえています。 このように、景気は回復していると言われていますし、その回復を示すような指標はいろいろと挙がってきています。しかし、人手不足は困ったことですから、それで景気回復を感じる人はそんなに多くないでしょう。 組織に雇われている立場の場合、有効求人倍率の改善は一見有利に見えます。長い目で見れば賃金水準も上がりそうですし、何よりも転職が容易になりそうですから。 しかし、何らかの理由によって人員が不足しても、その補充が難しくなるという事なので、組織に雇われて勤めているのならば、人手不足が困ったことであるには違いありません。 このような状況では、将来を見通すことは困難です。そのため、今利益を得られている事業が果たして将来も利益を得ることができるのかは誰にもわかりません。 また悪いことに、人口減少についてはある程度予測がつきますので、商圏内の人口の多寡によって業績が変動するような事業の場合(ほとんどの業種が該当しますが)、売上は漸減する傾向になってきてしまうでしょう。 そのため、将来の収益源へ組織の持っている資源を継続的に投資していく必要があります。 そうはいっても、今やっている事以外に未来に投資するなんて難しいといった声も聞こえてきます。 ただでさえ競争環境が厳しいので、納期も価格も品質も高い水準で両立していかないと今の売上を維持するのも難しいというのが本音でしょう。 ただ、今のままでは将来的に厳しくなるのが見えているわけですから、何らかの方策を考えていく必要があります。 そのためにすることは何でしょうか?それを考えていきたいと思います。 ■企業の目的とは 企業がやるべきこととして一番最初に上がることは、存続することです。というのは、企業は存続してさえいれば、その地域で雇用を生み、取引関係を通じて地域でお金を回し、うまく利益を獲得することができれば直接行政に税を納めることもできるからです。 例えば、1億円の売上を上げているけど、最終的には利益が出ていないような企業があるとします。このような企業はあんまり地域に貢献していないと早合点してしまいがちですが、このような企業が存在することで1億円のお金が地域で回っているという事実があります。 この企業があるおかげで地域の人は1億円分の買い物をすることができ、その企業へ商品を納品ししている企業は7千万円の売上を上げることができ、その企業で働いている人たちは2千万円のお給料をもらうことができ、そのほかの…といった形で地域の活力を生み出すことにつながるのです。 この意味から、企業は存続することが第一の社会貢献なのです。 しかし、存続することは適正な利潤を上げ続ける必要があり(短期的には資金繰りさえ何とかなれば存続できますが、長期的にはしっかりとした利潤を確保することが必要です)、適正な利潤を上げるためには、その企業が社会から求められる必要があります。 そして、社会から求められるためにはその企業が何をなすかといった理念が大切になってきます。 この理念がないと、やることがちぐはぐになってしまい貴重な経営資源を無駄遣いすることにつながり、結果として企業の存続が難しくなってしまいます。 もちろん、完全に無意味なことなどほとんどありませんので、企業の持っている経営資源が無限にあれば、すべてのことをやっていけばいいと思います。 しかし、残念ながらどのような巨大企業であっても経営資源が無限にあるという事はあり得ません。 そのため、自社の存続の可能性を高くするため、経営理念という一種の方向性を基に、やるべきことを確実にするために、やらないことを決める必要があるのです。 逆説的になりますが、今「するべきこと」は、今「しないこと」を決める事なのです。 ■やらないことが一番の改善 先日。新聞を読んでいたら興味深い記事が載っていました。 「経営課題が多い創業期の顧客をサポートする窓口を全店に設け、専門家と連携した創業支援をしている。支援先数は増えているが、目先ではなく将来の収益につながる地道な取り組みだ。」「こうした取り組みを強力かつ計画的に進めるため。事務の効率化・省力化により営業人員を捻出し顧客との接点の拡大につなげる。4月からの中期経営計画では150人をねん出する予定だ」 この取り組みのすごい所は、がむしゃらに頑張るといった精神論ではなく。具体的に事務の効率化・省力化で営業人員を捻出すると言い切っているところです。 やるべきことをやるために、やらないことを決めて取り組むという事は、確かにみんなが同意することだと思います。 しかし、総論はそうであっても、各論としてやらないことを決めることが難しいのです。その意味で、経営のトップがリーダーシップをもって取り組むというのは素晴らしい取り組みだと考えられるのです。 ■もっと頑張るという選択 さて、このようにやらないことを決めるなどというと、「そんなことを言わずに、もっと一人一人が頑張ればいいじゃないか」と考える人もいる事と思います。このように考える人は、おそらく高い能力をもって真面目に働いてきた人なのだと思います。 例えば、上の栃木銀行のケースでは、「創業支援は将来につながる大切なことだが、現在の事務作業も大切だ。だから、みんなで頑張って現状の業務を行ったままで、営業に投入する時間を拡大しよう」といった考え方です。 このような考え方で頑張ることは確かに尊いことですが、常に頑張らなければならないような方針では、意識してやるべきことに集中して取り組んでいる企業には太刀打ちできないでしょう。 少なくとも、経営戦略として考えるのならば、最初に考えるべきは、組織として再現性をもって高い業績を上げるための仕組みです。 というのは、頑張り続けるという行為は個人の資質に左右される部分が大きいため、再現性という部分に疑問が残る方策であるためです。 例えば抜群に頑張っている人が何らかの理由で職場から去ってしまったらどうなるでしょうか?その時に、前任者が頑張っていた成果を後任の人が同じだけ頑張って成果を上げることができるかどうかは誰にもわかりません。 しかし、やらないことを決めて、やるべきことに集中する仕組みが構築されていれば、組織としての成果を上げる可能性は格段に高くなります。 また、冒頭で指摘しているように、近年では採用難がかなり深刻になってきています。そのため、過度に個人の頑張りに期待し、恒常的に個人に負荷をかけるような組織体制にしていると、離職率が高くなってしまい採用コストや教育コストが高くなってしまう危険性があります。 そのため、頑張るのは最後の手段ぐらいに考えておいて、うまくいく方法を仕組みとして作っていく必要があるのです。 ■まとめ 今回、栃木銀行の取り組みの例に出して考えてみましたが、おそらくどの金融機関でも将来のために創業者の支援などには取り組んでいるはずです。 このような取り組みは非常に社会的意義のある取り組みですが、将来のために今取り組むべきことをやろうというのは、ある意味とても当たり前で全然目新しいお話ではありません。 しかし、その取り組みをするために足らないことを決めて時間を捻出するとはっきりと語る事はどうでしょうか? ともすれば、今やっている事はそのままに、人員も増やさずに新しい取り組みだけを増やすような意思決定をしがちではないでしょうか? そうではなく、やるべきことに集中するためにやらないことを明確にするという考え方。これこそが今後、企業が存続し続けるために大切な事ではないかと考えられるのです。 【参考記事】 ■環境は変わるものですが商売を継続するためには基本がやっぱり大切です(岡崎よしひろ 中小企業診断士) http://sharescafe.net/51978945-20170831.html ■翻訳アプリで接客時のデータを収集すれば、接客業で働く人が求められる能力が変わります。 http://okazakikeiei.com/2016/11/01/sekkyaku/ ■ウォークマンの最上位モデルをあえて30万円といった高価格で販売するソニーの戦略とは http://okazakikeiei.com/2016/09/09/sonywalk/ ■江崎グリコ「カプリコのあたま」という一見すると奇抜な商品は、手堅く考えられたコンセプトで市場に投入されている。(岡崎よしひろ 中小企業診断士) http://sharescafe.net/49426351-20160831.html ■自動運転技術が確立されたとき、中小企業にとってチャンスが訪れます(岡崎よしひろ 中小企業診断士) http://sharescafe.net/48236024-20160331.html 岡崎よしひろ 中小企業診断士 ツイート シェアーズカフェ・オンラインからのお知らせ ■シェアーズカフェ・オンラインは2014年から国内最大のポータルサイト・Yahoo!ニュースに掲載記事を配信しています ■シェアーズカフェ・オンラインは士業・専門家の書き手を募集しています。 ■シェアーズカフェ・オンラインは士業・専門家向けに執筆指導を行っています。 ■シェアーズカフェ・オンラインを運営するシェアーズカフェは住宅・保険・投資・家計管理・年金など、個人向けの相談・レッスンを提供しています。編集長で「保険を売らないFP」の中嶋が対応します。 |

